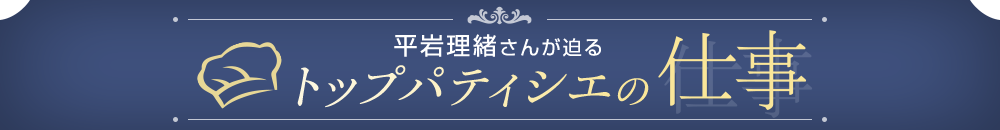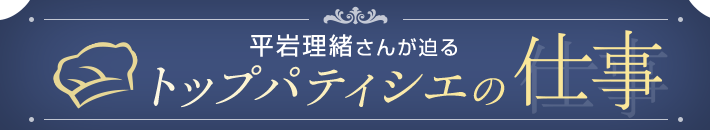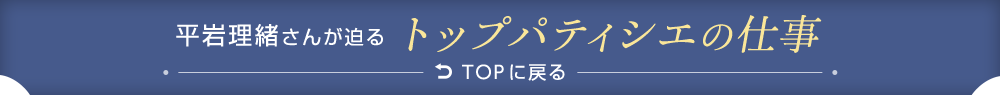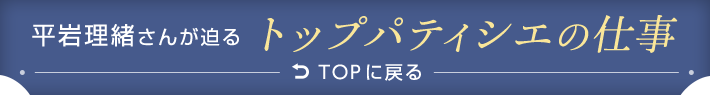菓子職人の方々へのインタビュー連載。今回は、東海エリアの人気店「シェ・シバタ」柴田武シェフにお話をお伺いしました。2006年以降、アジア各国にもお店を展開し、海外も飛び回っていらっしゃいますが、新型コロナウイルスによって世界が変わった今、日本人パティシエとして、今後やっていきたいこととは? 2021年には名古屋店を大きく改装しリニューアルオープン。そこから何を目指すのかなど、独自の視点で語っていただきました。
「和」を意識した店舗にリニューアルオープン
- 平岩
- こんにちは。リニューアルオープンされた名古屋店が気になっていましたが、ようやくお訪ねできました。さすが、柴田シェフらしく、カッコイイ店舗ですね!
- 柴田
- 改装すること自体は、耐震工事の必要性があって、4年程前から決まっていたことですが、昨年から準備を経て、2021年2月23日にグランドオープンしました。
- 平岩
- 格子戸で仕切られたような入り口や、吊り灯籠のような照明で、外から見ると和食店のようにも見えますが、バーカウンターなどもありますし、モダンでお洒落な雰囲気です。柴田シェフは、海外にもお店があり、外国でのお仕事も多いので、あえて「和」のイメージを意識されたのでしょうか?
- 柴田
- コロナ禍前は、外国もあちらこちらに行っていましたね。海外で店もやっていますが、その中で、「日本人」として見られる機会が多く、日本の店舗もインバウンドの効果で外国からのお客様が増えていました。和食も無形文化遺産として認められましたし、海外では日本料理店で使う「オマカセ」という言葉が浸透しています。そういった背景もあり、寿司店や和食の割烹をコンセプトとして、外国人デザイナーから見た「和」を基調としました。
お菓子の業界では、今まではフランスをオマージュしてきましたが、もう、そういう時代でもないと思います。


- 平岩
- 「日本らしさ」というのは、具体的にはどのように表現されたのでしょうか?
- 柴田
- たとえば壁塗りは、東京の左官職人さんにやっていただきました。あの、奥の壁に使っているのは、西陣の絹織物です。
外から見てもお菓子屋さんとわからないような外観ですね。こういう感じは、数年前に上海やバンコクで流行していました。自分がこれまで各地で見てきて、「これいいな」と思ったアウトサイドやインサイドのディテールを300点くらい写真に撮ってあり、それらを参考にしてデザインを決めていきました。
- 平岩
- 柴田シェフのInstagramを拝見すると、バーコーナーで提供されている予約限定のお任せコースの料理写真なども掲載されていますね。ピスタチオのパスタなど、美味しそう!と気になり、検索してしまいました。「たけバー」という名前でシェフが自らカウンターに立たれる形で運営されているのですね。利用するには色々なルールがあり、お店のファンでいらっしゃる常連のお客様向けの特別な空間という感じですね!
- 柴田
- 寿司屋のカウンターのような感覚で、よく言われる「映え」といったことでなく、作り立てのものを召し上がっていただきたいですね。フルーツグラタンやスフレといったデザートも出しますよ。いちじくのロティにタヒチバニラのグラスを添えて出すなど、温度にも配慮した、瞬間の美味しさを味わってもらいたいと思っています。

- 平岩
- ホームページにも、「静止画は大丈夫ですが、動画ばかり撮り、すぐに食べない方は次回からの予約はできません」という注意書きがありますものね(笑)。柴田シェフの思いに共感し、一緒に楽しめる方と共有したい場ということですね。
- 柴田
- 昔、バーテンダーの仕事をやっていたこともあって、バーが好きなんです。バー文化は、フランスより、イギリスやスペイン、イタリア、アジアなどの方が面白いですね。香港もイギリス文化の影響を受けています。東京の渋谷で「The SG Club(エスジー クラブ)」というバーを経営されている後閑信吾(ごかんしんご)さんという方とも、コロナ禍前は毎月行っていた上海のバーで知り合って、色々と刺激を受けました。
1年くらいかけて準備し、スタートしたんですが、料理をあれこれ一杯出しすぎて、レストランと思われてしまっている節もあります。レストランではなく、あくまでバーです。
- 平岩
- ここは、完全に柴田シェフがお1人で担当されているのですね?
- 柴田
- そうです。ただ、素材の使い方などは、スタッフにも伝えています。料理が出来る人のお菓子というのは、全然違うんですよ。でも最近の若い人達は、自分に投資しない傾向があり、あまりレストランに食べに行ったりしないんですよね。
店舗を展開していくと、シェフと直接関わらないスタッフも出てきます。その中でも、ものの考え方を伝えていきたいと思っています。
- 平岩
- お菓子屋さんには通常無い空間ですから、スタッフの方々にも、これまでに無い刺激になりそうですね。
他にも、店舗リニューアルに際して、意識されたのはどのようなことですか?
- 柴田
- 喫茶の席数は、以前より4席ほど減らしました。限られた敷地なので、色々と考えましたね。
非接触で精算が可能な自動レジも導入しています。これはコロナ禍になる前からやろうと思っていたことで、行列にならないよう、オペレーションを見直して、お客様をお待たせしないようにしたいと考えていました。今、コンビニでもそういう方向で、AIレジなども始まっていますし、キャッシュレスが広まっていますよね。やはり効率化が求められますし、販売接客の人材が減っているといった状況もありますので。
- 平岩
- 仰るとおり、自動レジを導入する菓子店は、ここ数年で増えてきていますね。
商品のラインナップについてはいかがですか?
- 柴田
- 焼き菓子ギフトを増やしています。生菓子はパティスリーの顔になるので、手をかけますが、やはり労働時間が長くなる。今は、種類を増やすのではなく、中身に力を入れていますね。そうすることで、お店のブランドイメージをつけやすくなります。労働時間を減らしながら、質のいいものを作って売っていくということが課題です。その一環として、今年の夏にはウォーターカッターも導入することにしました。

- 平岩
- 生菓子のショーケース内のプティガトーは20数種類ほどでしょうか。フランスAOP有塩バターの角切りとゲランド塩をのせた代表作の「エクレール オ ブールサレ」はじめ、鮮やかな青色が斬新なブルーベリーレアチーズケーキや、山のようにそびえ立つ背の高いパイシューのお菓子、丸く絞ったマロンクリームをドーム型に詰めて固めたようなモンブランなど、個性的で斬新なデザインや色彩のお菓子が目を引きます。半月型のアントルメも珍しくて面白いですね。
- 柴田
- オリジナリティは大切にしています。海外に行くと色々と面白い菓子とも出会い、ロシアなんかも奇抜なデザインのガトーがよくありますよ。実は、これまで苺のショートケーキというのを出していませんでしたが、リニューアルを機に出すようにしました。子どもの日など、イベントの時にはやはり人気ですね。
- 平岩
- それは意外でした!「ラ セゾン」という名前のお菓子ですね。

アフターコロナの世界情勢の中で
- 柴田
- うちも出店しているジェイアール名古屋タカシマヤも、2020年の10月からスイーツ売り場のリニューアルが始まり、今年3月にグランドオープンしましたが、商業施設はまだなかなか厳しい。オリンピックを経て少なくとも秋くらいまでは、コロナ禍の影響が好転するとは考えにくいですね。
- 平岩
- 柴田シェフは、海外でのお仕事も多いですが、コロナ禍以降は、なかなか現地に行けない状況ですよね。どのようにしていらっしゃるのですか?
- 柴田
- 海外との打ち合わせは、今はずっとリモートです。上海の店は2009年からやっていますが、去年の1-2月頃はやはり売り上げも厳しく大変でした。でも、3月からは黒字化しているんです。スタッフももう慣れているので、レシピがあれば彼らの方できちんと作れるようになっています。
香港の店舗は、2019年以降、民主化運動のデモが続いて、取り締まり強化で政情不安定となっていたので、やめました。これからは、シンガポールやマレーシアが面白いと思います。
- 平岩
- マレーシアは、2019年にフランスで開催された世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」でも、アジアの国として日本以外で初の優勝を遂げましたし、注目されていますね。海外との仕事は、政治運動の影響なども受けることがあり、なかなか難しそうです。



- 柴田
- 外国企業では店を開業できないといった制限もありますが、僕は現地法人と組んでやっているので、その点は問題ないです。今、タイの日航ホテル内に店舗のあるバンコクは、コロナに対応してロックダウンもあり、違反者への罰金なども厳しい。日本では罰則が無いので、様々な制限が中途半端になってしまっていますが、どこの国でも、比べるとメリットもありデメリットもある、一概に日本がいい、海外がいいとは言えないですね。
今のこの状況というのは、「オーボンヴュータン」の河田勝彦シェフのような先人の方々が苦労して海外でやっていらしたからこそ、「日本人だから」と世界で認められるようになった、ということだと思います。上海でお店を手掛けられた「メゾン・ド・プティフール」の西野之朗シェフなどもそうですね。それでも、もうかつてのような、「職人」が育っていく時代ではないと感じています。
- 平岩
- 今後のお菓子業界はどうなっていくか?どうしていくべきとお考えですか?
- 柴田
- お客様、特に若い方は、SNSの情報などを目にして、要求が高く、贅沢になっていきますね。でも我々はそれに応えなくてはならない。一方で、就職先としての飲食離れは進んでいます。中国でも、飲食店は面倒なのでやりたくない、という人が増えていますよ。1人でフリーランスでやっていく、みたいなパティシエが増えていますね。
- 平岩
- 確かに最近は、独立開業前からSNSで情報発信し、多数のフォロワーに支持されている若いパティシエの方が多いです。昔に比べて、自己プロデュースできる方が増えましたよね。
- 柴田
- 菓子業界が変わりつつある中で、新型コロナによってさらにそれが進みました。僕は、10数年前に海外に出て、今も存続できている。パティシエとしての可能性をもって、色々な選択肢を持てているということは、若い方達に、働く場は日本だけではないのだということを示せているのかなと思っています。
よく、「どうやったら海外に出られるんですか?」と聞かれますし、M&Aの話なども沢山いただきます。でも、ここまで来るのには、色々と損失もありましたよ。どことパートナーシップを組むのかということも、失敗しながらでないとわからないです。人間関係を構築していくのにも時間がかかり、4-5年は必要ですから、個人でやっていたら持たないですね。
- 平岩
- 海外で講習会をしたりすることはあっても、ブランドを展開するというのは、時間もかかり、大掛かりな話ですよね。
- 柴田
- 採用面接の時に、「海外の店舗で働けますか?」という子もたまにいます。コロナ禍の前までは、海外の人で、日本で働きたいという希望者もいましたが、本気で海外を見据えてやりたいという人は、この業界では少ないですね。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2021年05月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。